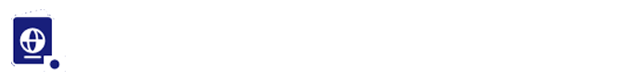永住許可申請は、申請者が要件を満たし、日本国の利益に合致すると認められる場合に限り、法務大臣の裁量で許可されます。つまり、許可は義務ではなく、法務大臣には判断の自由が認められています。
実際には、「法務大臣の広範な裁量権」は、不許可の理由を説明する際に審査官の根拠として用いられることが多く、申請者が要件を満たしているにもかかわらず不許可となる場合はこの理由によることが一般的です。
このような状況で重要なのは、いかにして一回の申請で永住許可を得るかという点です。申請者は、審査官が「問題ないので許可を出そう」と判断できるような資料を提出することが求められます。
このコラムでは、許可率を高めるための方法について解説します。
許可の確率を上げるには
永住申請で許可の確率を上げるためには、以下の4点が重要です。
1.資料の不備をなくすこと。
2.自分の強みを最大限に伝えること。
3.入国管理局の審査プロセスを理解すること。
4.審査官の心理を読むこと。
それぞれについて、以下に説明します。
資料の不備をなくすこと
下記に主な「不備」とその対処方法を記します。
1.要件を満たしていないのに申請をしたケース
このケースでは、不許可となる例が最も多く見られます。不許可となった場合には、必要な要件をすべて満たしたうえで再度申請を行う必要があります。再申請のタイミングは、不足している要件の内容によって異なります。そのため、再申請が可能になるまでに数か月程度の期間を要することもあれば、長い場合には数年待たなければならないこともあります。
以下に、主な要件を列挙します。
原則として、日本に10年間継続して在留していること
過去10年間の在留歴において、1回の出国が90日以上、または1年間の出国日数が合計で100日を超えた場合、在留の継続性が失われ、リセットされる可能性があります。このように継続性が途切れた場合、原則として、出国制限違反があった日から10年が経過した後に申請を行うことが望ましいとされています。
もしくは、現在の在留期間が10年未満であっても、申請が可能な他の在留資格に変更し、その資格に基づいて申請を進めることも選択肢です。
犯罪や重大な違反を起こしていないこと
特に注意が必要なのは、交通違反や資格外活動許可違反です。これらは「素行が善良である」という要件に反すると判断される可能性が高くなります。
交通違反が軽微であっても、5年間に5回以上発生すると不許可となる可能性が高く、件数が多い場合は「素行善良要件」や「国益適合要件」を満たさないと判断される可能性があります。そのため、違反から2~3年経ってから申請することをお勧めします。
当行政書士事務所で扱った案件でも、申請者ご自身の経歴や年収はまったく問題がなかったのですが、交通違反が多く、申請を断念した事例があります。
また、家族が、資格外活動許可違反(特に無許可のアルバイト)を行った場合も「素行不良」と見なされる可能性があります。
過去に犯罪が1回でもあった場合は、刑の執行が終了または免除された後、少なくとも10年間は申請を控えることが適切とされています。
自身で生活ができるだけの収入があること
永住ビザの取得には「安定した収入」が極めて重要な審査基準とされています。自立して生活できない場合、永住許可が認められる可能性は極めて低くなります。
「日本人の平均年収と同等以上」が必要とされ、これは最低条件とされています。独身の場合、年収300万円以上が一つの目安であり、扶養家族がいる場合は、一人あたり約70万円の追加収入が必要とされます。
納税や社会保険義務を適正に果たしてること
納税義務や社会保険・公的年金の加入義務に違反している場合、永住ビザの取得は非常に厳しいです。特に家族と同居している場合、自身に違反がなくても、家族の義務違反も影響します。
税金や保険料の滞納がある場合は申請の対象外となり、申請自体が厳しくなります。また、過去に滞納歴がある場合も審査の対象となるため、直近2年間以上にわたり納税・保険・年金の義務を継続して履行した実績が必要です。
転職頻度が少ないこと
永住ビザの審査では、「安定した収入」が重要な判断基準とされます。短期間に何度も転職を繰り返すと、収入の継続性や職業の安定性が疑問視され、「安定した生活基盤がない」と判断される可能性があります。
特に、転職による収入の大幅な変動や、転職の合間に無職の期間がある場合、経済的な安定性に欠けると見なされることがあります。これにより、将来的に継続的な収入を得られる見込みが薄いと判断される要因となります。
身元保証人が適切な人物であること
身元保証人になれるのは、日本人または永住者です。通常、身元保証人は、勤務先の上司、学生時代の恩師、すでに永住者の資格を得ている同じ出身国の友人に頼むことが多いです。これらの身元保証人は、申請者の信頼性を裏書きしてくれます。また、日本人と結婚している場合は、通常、配偶者が身元保証人となります。
一方で、身元保証人が見つからない場合、保証人代行サービスを利用することも考えられますが、この方法は避けるべきです。なぜなら、保証人代行サービスを利用したことが入国管理局に把握されると、申請が不許可となる可能性が高いためです。
行政への届出を適切に行っていること
引っ越しをした場合、引っ越し後2週間以内に市町村役場で在留カードの住所変更届を提出する義務があります。この届出は、滞在中の住所変更を正確に登録するために重要です。
また、退職や転職をした場合には、所属する機関に関する届出も必要です。この場合、退職や転職の後14日以内に、適切な機関に届出を行うことが求められます。
2.書類に誤記がある、または必要な資料が添付されていないケース
書類に正確な情報を記入し、不足している資料を提出することで解決できます。
3.以前の変更や更新時に提出した申請書と矛盾があるケース
過去の申請内容に矛盾があると、入国管理局に「事実と異なっているのではないか」という疑義をもたれる可能性が高まり、その結果、不許可になる可能性が高まります。さらに、入国管理局は、矛盾する情報を申請者に確認することなく、不許可とします。
4.申請前と申請後の状況が異なるケース
永住許可申請時に問題がなかった場合でも、その後に失業などが原因で年収が大幅に減少し、独立生計要件を満たさなくなることがあります。この場合も、不許可となる可能性が高くなります。
また、事情の変更を入管局に報告しないと、後に発覚した際に永住権が取り消される可能性があるので注意が必要です。
自分の強みを最大限に伝えること
以下は永住許可申請を有利に進めるためのポイントです。
理由書の内容に説得力がある
理由書は、申請者の経歴、永住権を取得したい理由、今後の日本での生活の予定などを説明するための書類です。審査官を納得させるために論理的な構成が求められます。また、具体的な出来事や数字を加えることも効果的です。
社会貢献やボランティア活動を行っている
永住申請においては、「日本国の利益になること」が重要な要素とされています。そのため、地域のボランティア活動に貢献し、その表彰を受けた者は、申請において有利に働くことがあります。
安定した住居が確保できている
持ち家であることは、永住許可にとって有益です。特に、住宅ローンを完済している場合は、さらに有利になります。
健康状態がよい
日本での生活を続ける上で、健康は欠かせない要素です。また、健康を保つ努力は、長期的な社会活動への参加を可能にします。さらに、自分が健康を維持するために取り組んでいる具体的な活動を示すことは有益です。
入管の審査プロセスを理解すること
1.申請を受理した案件の振り分けを行うため、主席審査官または所長が適切な者を振り分け担当者に指名します。
2.申請を受理すると、振り分け担当者は、電算処理を行った上で案件の振り分けが行われます。
3.資料の振り分けは以下の4つに分類されます。
(1)許可(交付)相当の案件:A案件、
振り分け担当者は、A案件に振り分けられた案件を速やかに決裁に回すこと、および(2)から(4)以外の案件については速やかに処分を行うことが明記されています。
(2)慎重な審査を要する案件:B案件
共通事項、就労資格、非就労資格、居住資格ごとに該当事項が決められているようですが、黒塗りのため詳細は不明です。
(3)明らかに不許可相当の案件:C案件
(4)資料の追完を要する案件:D案件
追完資料の提出後、A~C案件に再度振り分けられます。
出典:入国・在留審査要領第8編審査体制(法務省入国管理局)をもとに、当行政書士事務所にて編集
審査官の心理を読むこと
審査官が疑念を抱きやすい箇所については、あらかじめ十分な準備を行うことが求められます。たとえば、転職回数が多い場合には、その理由を理由書に記載したり、証拠資料を事前に添付することが望ましいです。
審査官は、提出された書類や説明文を通じて申請者の人物像を推測します。たとえば、家族の資格外活動違反がある場合には、反省の意を示し、今後の防止策を誠意をもって伝えることが重要です。
加えて、審査官の確認時間を短縮するために、提出書類や資料を整理し、見やすくまとめることが大切です。
そして最も重要なのは、審査官に「申請者は日本社会に十分に溶け込んでおり、日本の役に立つ」と思ってもらえる内容をふんだんに盛り込むことです。
まとめ
永住許可申請は、要件を満たすだけでなく、審査官に「この人なら許可しても問題ない」と納得してもらえる資料作成が重要です。不許可の多くは、要件の未達や書類の不備、説明不足によるものです。収入や納税状況などの各要件を正確に満たしているかを確認し、加えて日本への貢献や生活の安定性を示す資料を整えることが求められます。
理由書には動機や生活実績を具体的かつ論理的に記載し、審査官の視点でわかりやすく整理することが大切です。審査の実態を理解し、資料の完成度を高めることで、一度の申請での許可率を大きく向上させることができます。