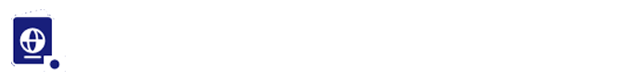2024年6月14日に入管法の改正案が通常国会にて成立し、公布されました。この改正は2027年4月に施行される予定です。これにより、日本における永住者の在留資格の取り消し条件がよりきびしくなり、永住資格を維持するための義務が強化されました。これにより、永住者は継続して日本社会に貢献することが要求されます。
このコラムでは、永住権の取り消しの現状、法改正の詳細、そして防止策について詳しく解説いたします。
永住権の基本的な要件とその重要性
永住権は、日本で長期的に生活し、社会に貢献する外国人に与えられる特別な資格で、通常の在留資格とは異なり、活動や滞在期間に制限がありません。
永住者となるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります:
- 1. 素行が善良であること(素行善良要件)
- 2. 経済的に独立していること(独立生計要件)
- 3. 社会に貢献すること(国家適合要件)
これらの審査基準に基づいて、永住権は与えられ、取得後は外国籍のままでありながらも、通常の在留資格と異なる特権を受けることができます。しかし、永住資格を持っていても、その維持には厳格なルールと責任が伴います。
現行の永住資格取り消し理由
永住資格が取り消される主な理由として、以下の要因が挙げられます:
①重大な犯罪や不正行為をした
麻薬や覚せい剤の使用や販売、暴行、不法入国など、重大な犯罪に関与した場合や、虚偽申請によって永住権を取得した場合は、永住資格が取り消されます
②再入国許可手続きを行わなかった
永住者が日本を出国する際、再入国許可を取得しなければ永住資格は取り消されます。有効期間内であれば何回も使用できる「数次有効な再入国許可」や空港で再入国EDカードにチェックを入れただけの「みなし再入国許可」などを必ず取得してから出国してください。
担当行政書士は、定められた年月日までに日本に帰国しなかった永住者の在留資格を持つ方から相談を受けた際、入管に問い合わせました。しかし、明確な対応策は持ち合わせていないようで、まず滞在国の領事館に確認するよう指示された経験があります。
2027年4月に施行される改正入管法の概要
今回の入管法の主な改正点は以下の4項目です:
- 1. 新たな在留資格「育成就労」の創設
- 2. 特定技能の適正化
- 3. マイナンバーカードと在留カードの一体化
- 4. 永住許可制度の適正化
この中でも、永住者に最も大きな影響を与えるのが「永住許可制度の適正化」です。
納税義務違反と永住許可制度の適正化
【永住許可制度の適正化について】
今回の改正では、永住許可制度を適正化するために取消事由が追加されました。具体的には、「故意に税金や社会保険料を支払わない」場合や「特定の刑罰法令に違反する」場合に、在留資格が取り消される可能性があります。
改訂版永住許可に関するガイドラインの「法律上の要件」の(3)イの下に注釈が追記されました:
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
【税金に関する永住資格取り消しの基準強化】
改正入管法により、税金の未払いが永住資格取り消しの理由となる可能性が高まりました。特に未納が長期間続いた場合、納税義務を果たさないことが永住資格取り消しに直結する可能性があります。
税金は国家の重要な資金源であり、未納が続くことで日本国の利益が損なわれ、社会の公正性も損なわれるため、今後は納税状況の管理が厳格化されると予想されます。
【社会保険料の未納と永住資格】
社会保険料(年金や健康保険料)の未納も、税金の滞納・遅延と同様に日本国の利益の喪失とみなされ、永住資格取り消しの対象となる基準が強化されます。社会保険料は社会保障制度を支える重要な資金源です。一方、2024年度は社会保障関係の費用が日本の歳出の約13分の1にものぼりました。
未納が長期にわたると納付をしている他の市民との間で不公平を生じる恐れがあります。条件が厳しくなった背景には、永住権を取得した外国人が、その後社会保険料を納付しなくなるケースが増えてきたからと推測されます。
厚生労働省は日本で暮らす外国人の年金や社会保険の納付状況を把握するため初めて実態調査を実施することを2024年5月に決定しました。よって、未納の場合は、今からでも納付を始めることをお勧めします。
【改正の背景と考え方】
この背景には、税金や社会保険料の支払いが本来の義務であるにもかかわらず、永住者には在留期間の更新がないために不払いが増加していることがあります。今回の改正は、このような不払いを防ぐための措置です。
一方で、永住者が税金や社会保険料を支払わない場合に、永住権が取り消されるのは、日本人に対する処置と比べて行き過ぎた罰則であるとの指摘もあります。横浜中華街の組合のように、永住者の間では議論を呼んでいます。ただし、一般的には、在留資格を変更することで引き続き日本に在留できる可能性があるようです。
令和6年入管法改正に伴う永住許可制度の適正化Q&A
Q1
永住許可の要件が明確化されたとのことですが、具体的にはどのような内容でしょうか。新たな要件が追加され、許可の基準がこれまでより厳しくなったのでしょうか?
Q2
改正後の入管法第22条の4第1項第8号における「この法律に規定する義務を遵守せず」とは、具体的にどのような場合を想定していますか?うっかり在留カードを携帯しなかった場合や、在留カードの有効期間の更新申請をしなかった場合にも、在留資格が取り消されるのですか?
永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な者を対象としています。これは大多数の永住者を対象とするものではありません。そのため、たとえばうっかり在留カードを携帯しなかった場合や、在留カードの有効期間の更新申請をしなかった場合に、在留資格が取り消されることは想定していません。
Q3
改正後の入管法第22条の4第1項第8号にある「この法律に規定する義務を遵守せず」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか?たとえば、うっかり在留カードの携帯を忘れた場合や、有効期間内に在留カードの更新申請を行わなかった場合でも、在留資格が取り消される可能性があるのでしょうか?
したがって、たとえば、うっかり在留カードの携帯を忘れた場合や、有効期間内に更新申請をしなかった場合などについて、直ちに在留資格を取り消すことは想定されていません。
Q4
例えば、差押えなどの処分によって、結果的に税金等の公租公課が支払われた場合、その未納の状況が事後的に解消されたと考えられますが、このようなケースは「故意に公租公課の支払をしないこと」には該当しないと考えてよいのでしょうか?
ただし、仮に取消しの要件に該当する場合でも、実際に取消し等の措置を講じるかどうかは、個別の事情を踏まえて判断されます。具体的には、公租公課の未納額や未納期間、支払に応じたかどうか、関係機関による対応への協力状況などが考慮され、事後的に未納状態が解消されたかどうかも判断材料の一つとなります。
Q5
改正後の入管法第22条の4第1項第9号に規定されている「刑罰法令違反」とは、具体的にどのような行為が該当するのでしょうか?例えば、過失による交通事故を起こし、道路交通法違反で処罰された場合や、罰金刑を受けた場合も、この規定の対象となるのでしょうか?
したがって、過失によって交通事故を起こし、過失運転致死傷罪で処罰された場合は、この規定の対象にはなりません。
また、道路交通法違反についても、本号で定める刑罰法令には含まれておらず、さらに、取消しの対象となるには拘禁刑(懲役・禁錮)を受けていることが要件とされているため、罰金刑に処せられた場合も対象外となります。
ただし、永住者であっても、罪名にかかわらず「1年を超える実刑判決」を受けた場合には、退去強制の対象となる可能性がある点には留意が必要です。
Q6
新設された取消事由に該当した場合、必ず在留資格が取り消されるのですか?
変更後の在留資格については、個々の外国人の在留状況や活動内容などを総合的に考慮し、日本に引き続き在留するうえで最も適切な在留資格が付与されることになりますが、多くの場合、「定住者」の在留資格が与えられると見込まれています。
Q7
「永住者」の在留資格が取り消された場合や「永住者」以外の在留資格へ変更された場合、その配偶者や子どもといった家族の在留資格はどうなるのでしょうか?
したがって、永住者の子が「永住者」または「永住者の配偶者等」の在留資格を有している場合、その在留資格には影響はありません。
また、配偶者の在留資格が「永住者」の場合も、その在留資格には影響がありませんが、「永住者の配偶者等」の場合は、「定住者」などの在留資格に変更する必要があります。
Q8
長く日本で生活しており、在留資格が取り消されても、本国に帰る場所がありません。このような場合でも、取り消しの対象となるのでしょうか?
この趣旨を踏まえ、永住許可の取消しが必要かどうかの判断にあたっては、対象者の日本社会への定着状況や生活実態などを総合的に勘案し、慎重に運用されることとなります。
出入国在留管理庁のホームページの「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)永住許可制度の適正化Q&A」をもとに、当事務所にて編集しました。
現状と将来の展望
現在、永住権に関する問題点として、不正行為や法改正の遅れが指摘されています。特に、一部の外国人による納税義務の未履行や社会保険料の滞納、不正な永住資格取得が問題となっており、その結果、外国人全体が迷惑をこうむる恐れがあります。
これらの課題に対応するために、永住資格の取り消し基準をより明確にし、強化することで、税金や社会保険料の支払いを確実にする方向に進んでいます。
一方で、今回の改正は新たな永住許可の要件を追加するものではなく、許可の要件を厳格化するものでもありません。むしろ、従来ガイドラインに記載されていた内容を法律に明記することで、永住者の義務を明確化し、適正な在留管理を目指すものです。
まとめ
永住者となることは日本での安定した生活を求める外国人にとって非常に重要なことですが、永住者であり続けるためには厳格なルールと手続きが求められます。
永住資格を守るための基本事項:
- 1. 犯罪行為の回避 – 日本の法律を遵守する
- 2. 再入国許可の取得 – 出国前に必ず取得する
- 3. 税金・社会保険料の期限内支払い – 延滞しないことが重要
特に重要なポイント:
納税や社会保険料の支払いは義務であり、その履行を怠ることは法律違反に該当します。延滞や未納があると、後に支払ったとしても審査時に不利な評価を受けることになります。 当初の納税(納付)期間内に履行することが求められます。
ただし、病気や失業などやむを得ない事情がある場合は、在留資格が取り消されることは想定されていません。また、取消事由に該当する場合でも、多くのケースでは「定住者」などの在留資格への変更が行われ、直ちに出国させられるわけではありません。
法律の改正により、今後はさらに永住者の適切な管理体制が進むことが予想され、永住者と日本社会がより良い共生関係を築くための基盤が強化されるものと思われます。
ご不安やご不明点がある際は、行政書士やFRESCの窓口に相談することをお勧めします。また、税金の支払いについてお困りの場合は、関係行政機関に相談することで、適切なサポートを受けることができます。
参考情報源:
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)」
- 出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」