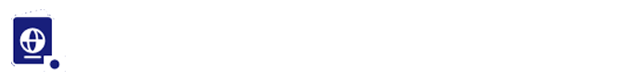はじめに
日本の永住権取得は難しいと言われています。永住ビザは審査基準が高く取得が難しい在留資格ですが、早期永住を目指す方は多くいらっしゃいます。しかし、実際に永住申請を自分で行った結果、残念ながら不許可となった方も少なくありません。
このコラムでは、永住申請が不許可になる主な理由と、許可を得るための再申請の方法について説明します。
永住許可申請の許可状況
日本の永住権取得は一般的に難易度が高い申請とされています。
以下は出入国在留管理庁による永住許可申請の推移です。
| 年度 | 申請件数 | 許可件数 | 許可率 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 50,907 | 28,924 | 56.8% |
| 2018年 | 61,027 | 31,526 | 51.7% |
| 2019年 | 56,902 | 32,213 | 56.6% |
| 2020年 | 57,570 | 29,747 | 51.7% |
| 2021年 | 64,149 | 36,691 | 57.2% |
2019年に永住許可に関するガイドラインが改定され、永住許可の審査はさらに厳格になりました。特に、東京や横浜などの大都市では、不許可率が60%を超えることも珍しくありません。
また、永住申請を認めるかどうかは法務大臣の裁量となっており、「これを満たせば必ず許可される」という具体的な審査基準は存在しません。
ただし、永住申請の不許可には一定のパターンがあります。そのため、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」に記載された条件を確実にクリアし、適切な方法で申請すれば、永住権を取得できると担当の行政書士は考えています。
では、具体的に不許可となる2つの理由について見ていきましょう。
不許可理由その1:【申請書類に不備がある】
最初の理由は、入国管理局に提出する申請書類に不備があるため、不許可となるケースです。
具体的な不備としては、
・書類の記載内容が不完全である(軽微なミスであれば申請時に修正が可能です)、
・申請内容に矛盾があり、一貫性がない(以前の更新時に提出した情報との照合も行われます)、
・理由書などでの説明が不十分で、審査官の疑念を晴らせない、
・添付する証明資料が不足している、
などが考えられます。
このようなケースでは、適切な書類を再作成し、再度申請を行うことで許可される可能性が高まります。また、不備が修正できる場合は、すぐに再申請することをお勧めします。
一方で、外国人にとって比較的難しい点は、
・理由書に記載すべきポイントを把握できていない、
・説明をした方が有利な事柄と、不利になる事柄を明確に判別できていない、
・証拠資料の種類を特定できず、収集方法がわからない、
・全て日本語で作成しなければならない、
・添付資料に外国語のものがある場合、日本語訳をつける必要がある(英語以外)、
などです。
中でも、説得力のある「理由書」を作成することは非常に重要です。理由書の出来具合によって、許可の80%が決まると公言する行政書士もいます。
永住申請では、「永住許可申請理由書」を必ず提出しなければなりません。この理由書は、「なぜ永住ビザが欲しいのか」を説明する最も重要な申請書類です。「永住許可申請理由書」を作成する目的は、審査官に対して「この人に永住権を与えることは日本にとって有益である」と確信させることです。
一方で、「永住許可申請理由書」には決まったフォーマットがなく、自由に作成することができます。逆に言えば、作成テクニックを身に着けていないと、ポイントを抑えた内容が作成できないということです。永住申請は面接ではなく書類審査だけで許可、不許可が決定されるため、理由書の役割は一層重要です。
理由書を作成する際には、インターネットで参考資料を検索する方も多いでしょう。ただし、インターネットに掲載されている理由書の記事は、記載すべき項目など一般的な情報が多く、あなたの状況に特化したものではありません。肝心なのは、あなたの状況に合わせて審査官を納得させる内容に仕上げることです。
これらの困難を克服するために、行政書士などの専門家に相談するのも良いかもしれません。
不許可理由その2:【申請要件を満たしていない】
永住権取得が難しい2つ目の理由は、多くの申請要件を満たさなければならないことです。さらに、これらの要件を満たしているかどうかを判断することは容易ではありません。
すべての申請要件を満たさない限り、たとえ行政書士などの専門家に依頼したとしても不許可となります。このような場合、申請要件がクリアできる状況になるまで待つしか手立てはありません。
申請要件を満たしていないケースのTOP9は以下の通りです。
1. 世帯年収が足りない
永住ビザの取得には、将来にわたり安定して生活できるだけの世帯収入や資産が必要です(独立生計要件)。世帯年収の目安は、日本人の平均年収とほぼ同じ300万円です。また、配偶者や子どもの扶養者がいる場合は、扶養者1人あたり約70万円の上乗せが必要となります。
最低世帯年収額が要求される継続年数は在留資格ごとに異なります。
・就労ビザの場合:5年間継続していること
・日本人の配偶者等、永住者配偶者等の場合:配偶者は3年間、子どもは1年間継続していること
・高度専門職の場合:ポイント計算表のポイント70点以上なら3年間、80点以上なら1年間継続していること
注意点
・家族滞在ビザを持つ配偶者が稼ぐアルバイト代は世帯年収に加算できません。一方、就労ビザを持つ配偶者の収入は世帯年収に加算できます。
・過去に年収が300万円を少し下回っていた場合でも、勤務年数が相当であり、年収が上昇傾向にあれば、永住許可が下りることがあります。
2. 扶養人数が多すぎる
世帯年収に対して扶養人数が多い場合、安定した生計を今後も維持できるのかという懸念から、永住ビザが不許可となる原因となります。
また、外国人の中には、扶養家族が多ければ多いほど税金が安くなることから、本国にいる親や兄弟を扶養家族としている場合があります。節税目的で本国に送金をせずに名義を使用している場合は「脱税」と見なされ、この点でも不許可の原因となります。
節税目的で扶養に入れている場合は、その扶養者分の年収を稼ぐか、さもなければ扶養から外し、さかのぼって修正申告をしてください。
3. 外国への出国日数が多いまたは出国頻繁が高い
1年のうちに1回の出国で90日以上、または年間で合計100日以上出国している場合、連続在留年数がリセットされ、居住要件を満たさなくなる可能性があり、不許可となることがあります。
ただし、会社の命令による長期出張の場合は、その理由を理由書等で説明すれば許可されることがあります。一方、出産や育児のために母国に里帰りし長期間出国する場合は、個人の都合と見なされ、不許可になる可能性が高いです。
4. 公的年金や健康保険を適正に納付していない
2019年8月以降、日本国の利益を強化する観点から、年金の支払記録の提出が永住申請の必要書類となりました。
給与所得者である会社員であれば、給与から年金や健康保険料が天引きされるため問題はありませんが、個人経営者や個人事業主で自ら国民年金や国民健康保険を支払っている場合は注意が必要です。また、会社員の方でも転職活動を行った場合は、転職活動期間中に納付漏れがないか確認することをお勧めします。
年金や健康保険の未納がある場合でも、2年間納付期限を守って納付すれば、再度永住申請が可能です。
さらに、配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している場合は、配偶者の年金や保険料の納付状況も審査対象となるため、注意が必要です。
5. 交通違反
交通違反も素行要件の一つです。軽微な交通違反であっても、過去5年で5回、または直近の2年間で3回以上の違反がある場合、永住許可が下りにくくなります。運転記録証明書を警察署で取得し、確認してください。
6. 在留資格で許可された活動内容以外の活動をしていた
配偶者や子どもが「資格外活動許可」を得ていても、週28時間を超えてアルバイトを行った場合、永住申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
7. 在留期間が3年以上ない
永住申請を行うには、法律上、現在の在留資格の最長の在留期間(5年)を保持している必要がありますが、実際には3年以上あれば問題ありません。1年の在留期間では申請はできません。
8. 適切な身元保証人が見つからない
身元保証人は日本人または永住者でなければなりませんが、身元保証人が見つからないからといって「身元保証人代行サービス」を利用すると、それだけで不許可になる場合が多いため、絶対に利用しないでください。
9. 転職して一定期間が経過していない
転職後、まもない申請は不許可になる可能性があります。「勤務状況や生活が安定していない」と審査官に判断される可能性があるためです。
日本の永住権の申請で不許可となった事例
1.システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが、その勤務だけでは日本経済に貢献しているとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
2.日本で起業し会社経営を行っているが、その投資額や利益額からは顕著な業績とはいえず、日本経済に貢献しているとは認められず不許可となった。
3.外国人の子どもの教育を行う機関において教師として活動していると申請があったが、その活動だけでは社会的貢献には当たらないと判断され不許可となった。
4.約1年間高校で教師を務め、通訳のボランティア活動も行っていたため申請を行ったが、その活動のみでは社会的貢献に該当しないとされ、不許可となった。
5.Aさんの在留歴は6年11か月です。語学指導助手として来日し、3年間は日本の中学校で、以降の約4年間は高校で英語教育に従事していたものの、日本の大学における常勤またはそれに相当する教授、助教授、講師としては認められず、高等教育の水準向上に貢献した者とは見なされなかった。
※出入国在留管理庁のサイト掲載内容をもとに弊所が一部変更しました。
不許可になった後の再申請の方法
永住申請が不許可になるケースは決して珍しくありません。ここでは、不許可になった場合の対処方法を説明します。
永住申請が不許可になると、「不許可通知書」というハガキが送られてきます。ハガキには、不許可の理由について「出入国管理及び難民認定法第22条第2項第2号に適合すると認められません」とだけ書かれており、これ以上の詳しい説明はありません。
そのため、不許可の具体的な理由を知りたい場合は、永住許可申請をした入国管理局を訪問し、審査官から直接不許可の理由をヒアリングする必要があります。
再申請は、以下の5つのステップで進めていきます。
Step 1
ヒアリングを行う前に、推測される不許可の原因を特定し、その推測した不許可の原因が本当に真の不許可原因であるかをヒアリングを通じて検証します。
ここで問題となるのは次の3つです。
1.ヒアリングを行う審査官は,必ずしも不許可の決定を下した審査官とは限らない
2.入国管理局は不許可の理由を伝える必要はありますが、すべての理由を伝える義務はありません。たとえ不許可理由が5つあっても、1つしか教えてもらえないかもしれません。
3.不許可理由を直接聞くことができるチャンスは,一人1回だけです。5回不許可が続いても,ヒアリングができるのはたった1回です。
したがって、「不許可の原因は何か」「不許可の原因はいくつあったのか」「どのようにすれば不許可にならなかったのか」といったことを明らかにする必要があります。そのためには、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。行政書士は、直接審査官から不許可理由を聞くことが認められています。
また、行政書士は審査のポイントを把握しているため、さまざまな情報を引き出し、再申請のための重要なポイントを正確に把握することができます。
Step 2
不許可理由を特定した後は、それらを克服するための戦略を考えます。
例えば、年収基準を満たしていないことが不許可の原因であれば、年収要件を満たすための複数の案を考えます。
Step 3
不許可理由を改善するための施策を実行します。
不許可理由をすぐに改善できない場合は、改善できるまで待つ必要があります。永住申請の場合、不許可理由をクリアするためには数年待たなければならないこともあります。
Step 4
不許可理由をクリアできたら、永住権の再申請の準備を進めます。
その際、特に重要なのが「理由書」と「証拠資料」です。
理由書では、不許可理由をどのように克服したかを審査官に分かりやすく、論理的に説明することが必要です。
なお、一度不許可になった案件はより綿密に審査されるため、不許可理由が確実に改善されたことを強調することをお勧めします。
Step 5
いよいよ、不許可理由を改善した資料を提出します。
永住ビザの申請は何回でも行えますし、不許可から再申請までの間隔に関する決まりもありません。
したがって、不許可理由が改善され、証拠も入手できたら、積極的に再申請を行いましょう。
まとめ
永住許可申請が不許可になった場合でも、簡単には諦める必要はありません。
永住権申請が不許可となる主な理由は、「申請書類の不備」と「申請条件を満たしていない」の2つです。
申請書類に不備がある場合、納得力の低い理由書や証拠資料の不足が問題となることが多いです。これらを適切に改善すれば、再申請で許可される可能性は高まります。
一方、申請要件を満たしていない場合には、収入基準などの要件を満たすことで再申請が可能となります。永住ビザの再申請においては、不許可となった理由を正確に把握し、それに対する改善策と裏付け証拠が重要です。
さらに、永住ビザ申請では、理由書を論理的に構築することが極めて重要です。理由書は、「なぜ永住ビザが必要なのか」を審査官に説得力をもって伝えるための最も重要な審査書類であり、その出来栄えが許可の結果に大きく影響します。
不許可理由に対する具体的な対策を講じ、それを適切に理由書や添付資料で説明することで、再申請の成功率を大幅に高めることが可能です。当行政書士事務所では、長年の営業経験に基づいて「要件を満たしていることの確認」「証拠集め」「論理的に永住理由書への落とし込み」を行い、審査官が納得するストーリーを作り出します。その結果、再申請の許可を得られる確率が大きく向上します。